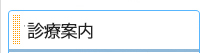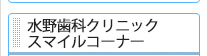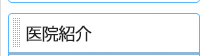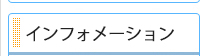|
|
 |
| よくある質問 |

 よくある質問 よくある質問 |

 歯周病について 歯周病について |

 検査と歯石取りはセットですか? 検査と歯石取りはセットですか? |
 |
現在は健康保険を利用する場合、
基本的には、検査なしの歯石取りは行なえません。
これは、歯石を取る前に検査によって状態を確認してから、
歯石を取る決まりになったからです。
歯石を取り終わった後も、再び検査が行なわれたりします。
これは治療の効果や歯肉の反応などを、
歯石を取る前の検査結果と比較するためです。
そしてその後の治療の方針などに利用します。
このため歯石を取る前、取った後の検査はよく行なわれています。
|

 歯肉の検査はどんなことするの? 歯肉の検査はどんなことするの? |
 |
【歯周ポケット測定】
歯と歯肉の境界部にある歯周ポケットと呼ばれる溝の深さを、
専用の器具(先の細い棒状の器具)を挿入して測定します。
標準的には1〜2ミリ程度で、一般に深さが深い程、
歯周病が進行していると考えられます。
4ミリ以上で要注意。6ミリ以上は、かなり進行していると考えられます。
【出血の有無】
歯肉から自然に出血しているかを調べるのではなく、
歯周ポケットに器具を挿入した際に出血するかを調べます。
数字に○印が付けられたりします。
健康な歯肉は、出血はなく、痛みもあまり感じません。
歯周ポケット内部の炎症がある歯肉の場所のみ出血します。
【歯の動揺】
歯のぐらつきの程度を調べます。0から3などの数字で表されます。
数字が大きくなるほど、歯が動いていると判断されます。
0が健康な状態、3でかなり歯周病が進行した状態の歯の動きと考えられます。
【口腔清掃状態】
歯周病や虫歯の原因となるプラークがどれだけ歯に付着しているかを調べます。
歯と歯肉の境目の部分に付着しているプラークの場所を記録します。
ときどき検査の段階で痛みを感じたり出血が起こったりすることがあります。
しかし決して検査でわざと歯肉を傷つけるようなことは行なわれません。
検査で痛みや出血が起こるのは歯周病の炎症が、すでに起こっている場合です。
|

 歯周病は歯と歯の間がなりやすい? 歯周病は歯と歯の間がなりやすい? |
 |
歯と歯の間は、虫歯に関して言えば、
「トンネル虫歯」などが、出来やすくなっています。
これは、歯と歯が接触している部分は、
ブラッシングがうまく出来ないため虫歯になりやすいからです。
実は歯周病も同じように、歯と歯の間の根元部分は、
ブラッシング時の毛先が届きにくいため、歯石などが溜まりやすく、
歯周病になりやすい要注意ポイントと考えられます。
※トンネル虫歯
歯と歯の境目から、歯の内部に向かって
トンネルを掘るように進行する虫歯のことです。
|

 矯正歯科について 矯正歯科について |

 どうして良くない歯並び(不正咬合)になるのですか? どうして良くない歯並び(不正咬合)になるのですか? |
 |
原因と思われるものをいくつか挙げてみます。
何か思い当たるものがありますか?
・遺伝(家族や親戚で同じような歯並びの人はいませんか?)
・虫歯で乳歯が早く抜けてしまい、
永久歯への生え変わりがスムーズに行われなかった
・外傷
・咬むことの不足による顎の骨の発育不良
・舌癖や指しゃぶり
・鼻疾患(口で呼吸をよくしている、など)
・唇や顎の筋肉が強い場合
・片側だけで咬む癖
・ほおづえをつく癖
これらが原因で、歯並びが悪くなる事もあります。
「何だかおかしいな?」と思ったら、お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:0568-81-3068 / メールはこちらから |

 歯並びが悪いとなぜいけないのですか? 歯並びが悪いとなぜいけないのですか? |
 |
・歯がきれいにみがけないので虫歯になりやすく、
また、歯ぐきがはれる歯肉炎になったり、もっとひどくなると、
歯を支えている骨の病気の歯周病(歯槽膿漏)になったりします。
・食べ物を良く咬む事ができません。
そのために消化器官に悪い影響を与えたり、
顎の骨の発育に支障をきたしたりします。
・笑った時などに人に与える印象があまり良くないので、
思いっきり笑えなかったり、手で隠したりする為、
心理的障害やコンプレックスにつながります。
・正しい発音がしにくかったり、電話や普通に話している時に
聞き取りにくい言葉があったりします。
・咬み合わせがあまりひどいと、口を開ける時に
顎の関節から音がするようになったり、
さらに進むと痛みを伴う顎関節症を起こす可能性があります。
・横顔などの口もとが気になる。
(唇が出っ張っていたり、反対に引っ込んでいたりする)
|

 矯正治療の期間はどのくらいかかりますか? 矯正治療の期間はどのくらいかかりますか? |
 |
その方の症状や治療の内容によって違いますが、
部分的に治す人で1〜2年、
全体的に治す人でだいたい3年くらいかかります。 |

 通院はどのくらい必要ですか? 通院はどのくらい必要ですか? |
 |
治療が始まってからの通院は月に一度、治療時間は30分程です。
また治療内容によってもっと時間のかかる時や、
2〜3週間先位に来てもらうこともあります。
治療が始まる前や治療後、保定中の患者さんは
1年に2度くらいの定期検診が必要です。
|

 費用はどのくらいかかりますか? 費用はどのくらいかかりますか? |
 |
これも患者さんの症状や内容によって違ってきますが、
当院では40〜80万円の間となります。
はっきりとした金額は検査結果を検討し、診断時にお話します。
|

| |
 |
矯正治療中、虫歯はできやすくありませんか?
又虫歯ができたらどうすればいいのですか? |
| |
 |
装置が付いて歯みがきがしにくい分、多少虫歯になりやすいかもしれませんが、
今までより細かい所を丁寧にみがいていれば虫歯にはなりません。
また、歯が動いていくうちに今まで重なり合っていて
見えなかった所の虫歯が見つかることもあります。
そんな時は当院で虫歯の治療にじゃまな装置は一時はずしますので、
かかりつけの歯医者さんで治してもらってください。
月に一度の通院時には、歯肉や虫歯のチェックも行っています。 |

 矯正治療中に、転勤や転居の場合は? 矯正治療中に、転勤や転居の場合は? |
 |
転勤や転居の場所がわかった時点でお知らせ下さい。
通院が難しい場所のときは、海外を含め転居先に近い、
信頼できる先生をご紹介いたします。
また矯正費用は治療済みの分だけいただき、残金はお返しします。 |


 小児歯科について 小児歯科について |

 フッ素塗布はいつから始める? フッ素塗布はいつから始める? |
 |
理論的には生えてきたらすぐに塗るほうが、
歯質と反応しやすいと言われています。
しかし、乳歯の生え方と協力状態等を考えると、
1歳6ヵ月前後を目安にしたほうがよさそうです。
3〜4ヵ月間隔でお口のチェックを受け、
その時にフッ素を塗ってもらうとよいでしょう。
永久歯が生え揃う15歳頃までは、定期的に続けていきましょう。 |

 乳歯が抜けていないのに歯が生えてきましたが? 乳歯が抜けていないのに歯が生えてきましたが? |
 |
下の前歯にはよくある事です。
歯がグラグラしているのであれば、経過を見ておいて良いのですが、
歯磨きや食事の時に不便を感じることがあれば
歯科医院で抜いてもらいましょう。
また、動揺がほとんどなくしっかりとしている場合は、
歯科医院で抜歯が必要かをチェックしてもらってください。
|

 歯磨きしているのに歯が着色してきます・・・。 歯磨きしているのに歯が着色してきます・・・。 |
 |
お茶椀に着く茶渋と同じです。
お茶などに含まれる色素が歯の表面に着いただけなので、
とくにむし歯の原因にはなりません。
歯ブラシで磨いてもなかなか取れないような場合は、
歯科医院で専用の磨き粉を使った機械による清掃をするときれいになります。 |

 上の前歯にすじが入り込んで隙間ができています。これって大丈夫? 上の前歯にすじが入り込んで隙間ができています。これって大丈夫? |
 |
上唇を上にひっぱった時にできる「すじ」を、
上唇小帯(じょうしんしょうたい)と言います。
1歳半ぐらいまでは比較的太く厚みがありますが、
成長するにつれて徐々に上の方に位置してくることがあります。
そのため小帯をすぐに切除するのではなく、様子を見る場合がほとんどです。
また、ケガによって自然に切れることもありますので、
前歯4本が永久歯に生え替わるまではそのまま様子を見ましょう。 |

 指しゃぶりと、歯の成長に関係があるって本当? 指しゃぶりと、歯の成長に関係があるって本当? |
 |
指しゃぶりを頻繁にしていると、
上下の前歯が咬み合わなくなったり、出っ歯気味になったりします。
これは指(多くは親指)によって上の歯は外側に、
下の歯は内側に押されるためです。
指しゃぶりの原因としては、母乳を吸う反射の延長、
あるいはストレスや欲求不満の解消などが考えられます。
4歳を過ぎると1人遊びの時期から脱し、
友達や周囲に関心が向くようになり徐々に減ってきます。
無理に止めさせると、精神的あるいは情緒的な問題が出る可能性があります。
本人の理解と協力が得られるようになる年齢(7〜8歳)まで、
様子を見るのが一般的です。
いずれにしても、お子さんとのスキンシップが最も大切です。 |

 癖で歯ぎしりをしているのですが、やめさせたほうが良いのでしょうか? 癖で歯ぎしりをしているのですが、やめさせたほうが良いのでしょうか? |
 |
乳歯が生え始める生後7ヶ月から永久歯列が完成する15歳までは、
お口の中が変化に富んだ時期です。
この時期には、噛み合わせも微妙に変化しています。
上下の歯が一部分で当たる所を、
歯ぎしりすることにより、均等に噛めるようになります。
一種の生体の調節機構と考えてください。
もちろん、ストレス等の原因もありますが、歯がしみたり痛みが出たり、
あごに異常が出ない限りは、永久歯列完成期(15歳)まで様子を見ていいでしょう。 |

 反対咬合について 反対咬合について |

 反対咬合って、自然に治るでしょう? 反対咬合って、自然に治るでしょう? |
 |
永久歯が生えるとき、自然に治ることがあります。
ただし、かなり少数例です。
反対になっている下の歯の前歯が、5〜6本。
逆の噛み合わせが深い。近親に反対咬合の人がいる。
これらの場合、自然に治る可能性は、極めて少ないと考えてよいでしょう。 |

 永久歯がはえるまで、様子見を勧められましたけど? 永久歯がはえるまで、様子見を勧められましたけど? |
 |
「・・・大丈夫ですか?」というご質問をよく戴きます。
自然に治る場合もあります。しかし、それはかなり少数です。
ご相談できる歯医者に診て貰い、意見を求めることをお勧めします。
私たちは、大半の方に早期初期治療が必要と考えています。 |

 反対咬合、治した方が良いの? 反対咬合、治した方が良いの? |
 |
不正咬合であるから、成長発育が遅れるという事は基本的にありません。
しかし、サ行、タ行の発音に、特徴的な舌足らずのしゃべり方になる。
食べ方がワニの様だ。という様な特徴が現れることがあります。
しゃべり方にも、食べ方にも問題が現れます。
しかし、私たちが治療を勧める第一の理由は審美的な理由です。
反対咬合特有の顔貌に、劣等感を感じることがあります。
心の負担を軽くし、生活の質の向上が目標です。 |

 早く治した方が良いの? 早く治した方が良いの? |
 |
噛み合わせを逆のままにしておくと、下顎骨が過成長し易い状態が続きます。
下顎骨が取り返しの付かない程大きくなってしまう前に、
逆のかみ合わせは治しておくべきです。
早ければ早いほど、ご本人の負担は軽くて済むと思います。
年齢が高くなると、治療法の選択肢が狭くなります。
過成長し、大きくなってしまった「下顎骨を切断して縮める」という手術法も、
選択肢に上がってきます。 |

 どうして反対咬合になるの? どうして反対咬合になるの? |
 |
口には多くの筋肉が整然と並び、機能しています。
舌は、代表的な筋肉の固まりです。
きれいな歯並びの人の舌は、嚥下(のみ込む)する時、
上顎を押さえつけるように、ぴったりと収まります。
しかし、反対咬合の人は、上顎には着きません。
嚥下の都度、舌は下顎を前方に押します。
従って、上顎は小さく、下顎は大きくなってしまうと考えられています。
すなわち、口腔周囲の筋肉が正しく機能しないと、
不正咬合になるという事です。 |

 どうやって治すの? どうやって治すの? |
 |
筋機能のアンバランスが、不正咬合を造ります。
バランスを整え、調和を取り戻せば、不正咬合は回復します。
反対咬合の原因のひとつは、舌が低い位置で機能していることです。
ですから治療目標は、まず、舌を挙上して上げることです。
その様に、バランスを取り戻す器具が機能的顎矯正装置「ムーシールド」です。
就寝中使用します。取り外しできる装置ですから、うまく使えなかったり、
諸条件によっては、期待する効果を得られないこともあります。
主治医に充分相談の上、ムーシールドを使うことをお勧めします。
|

 一度治したら、もう大丈夫? 一度治したら、もう大丈夫? |
 |
ムーシールド治療法は、たいていの場合、およそ1年間を目標に治療します。
一度治したら、「もう大丈夫」という人が大半です。
しかし、成長がスパートする頃、再治療を必要とする場合があります。
定期健診は重要です。
女性は15歳〜16歳。男性は17歳〜18歳まで成長します。
その頃まで、定期健診を続けることが理想です。 |

 反対咬合は遺伝する? 反対咬合は遺伝する? |
 |
反対咬合は、遺伝します。
顔形は、ご両親に似ます。残念ながら、反対咬合の家系があります。
しかし、早めに対処することで、かなり改善できると考えています。
いずれにせよ、遺伝の有る無しに関わらず、早めに受診することを、お勧めします。 |



|
|
COPYRIGHT(C)2012 水野歯科クリニック ALL RIGHTS RESERVED.
|
|